|
| �d�q��ψ������R�~���j�P�[�V�����ψ���� |
|
�@�d�q��ψ���ł́C2014�N�x�܂łɎ��{���Ă����{�w��S�̂Ɋւ����̓d�q���̐��i��
�Ȃ�тɍ���̏��Z�p�̗L�����p�Ɋւ���c�_�����܂����B���ɁC�ߔN�͈ȉ��̊����Ɏ��g��ł��܂����B
�E���[���j���[�X�z�M
�E�����p�y�[�W�̍\�z�Ƃ��̗L�����p�ɂ��Ă̌���
�EJCI�z�[���y�[�W�̈Ӌ`�Ɖ^�c���@�Ɋւ���c�_
�E�d�q��c�V�X�e���Ɋւ���c�_
�E�N�����������Ǔ��e�V�X�e���̊m�F
�E�N�����p�̃A�v�������DVD�Ɋւ���m�F
�@��L�̂悤�ɁC���łɖ{�w��S�̂Ɋւ����̓d�q���͂قړ����̖ړI��B�����Ă���C
���Ȃ�ۑ�Ƃ��āC�X�Ȃ�Љ�j�[�Y�ɑΉ��ł���悤�C�{�w��z�[���y�[�W�����
���[���j���[�X�Ȃǂ�IT�����p������M�̊������ɂ��ċc�_�����悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�@���̂悤�ȏ���C���Ȃ�ۑ�Ɏ��g�ސV�ψ���Ƃ��āu���R�~���j�P�[�V�����ψ���v��
�ݒu���C������ɑ啔���̎��Ƃ��ڂ��ƂƂ��ɁC���̓d�q���Ɋւ���{�ψ���̎��Ƃ��k�������邱�Ƃɂ��܂����B
�{�N�x�ȍ~�C�d�q��ψ���̊����́C�{�w����ǂ̗v���Ɋ�Â��C���̓d�q���Ɋւ���T�|�[�g�����S�ƂȂ�\��ł��B
�@�Ō�ɁC�d�q��̊����ɂ����āC�l�X�ȃA���P�[�g�������{���C�{�������邢�̓R���N���[�g�H�w�Ɋւ��
�����̊F�l�̂����͂�����܂����B�{�w��z�[���y�[�W�̃��j���[�A����[���j���[�X�̔z�M�Ȃǂ̐��ʂ��c�����Ƃ�
�ł��܂����̂��C�l�X�Ȍ`�ł����͂����������F�l�̂������ł��B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
|
|
|
|
| �d�q��ψ���̂���� |
|
�@�{��́A1996�N��JCI�z�[���y�[�W���쐬���Č��J�������A�}���ȓd�q��Љ�ɑΉ����邽�߁A
2002�N�ɓd�q��ψ����ݒu���A����Ɩ����܂߂��d�q���ɂ��Č������J�n�����B
���̌��ʁA2002�N�ɂ��ŊJ�Â����R���N���[�g�H�w�N�������AWEB����_�����e���s���悤�ɂ��A
�܂��N���_���W������ł���CD-ROM�łɕύX���Ď��������̌�������}�����B
�@����ɁA��2003�N�̑��_������́A�_�����ǃV�X�e���̍\�z�ɂ�肷�ׂĂ̓��e�_���̍��ǂ�WEB�ōs����悤�ɂ����B
�@�܂��A�ߋ��̌������̓d�q���ɂ��A�N���_���W�̑�P������S�Ă̘_�����z�[���y�[�W��Ō����ł���悤�ɂ����B
�@2005�N9������̓��[���j���[�X�����s���A�{����x���̍Â��̏Љ��R���N���[�g�H�w���̓��e�Љ���s���悤�ɂ����B
�@2012�N�ɂ͉����p�y�[�W�𗧂��グ�A��2013�N����͉�A�_���W�Ƙ_���W�̉{�����̓���̎������ł���悤�ɂ��Ă���B
�@2013�N�ɖ��É��ŊJ�Â����R���N���[�g�H�w�N���������A�v�������J���A���\�_���̓d�q�{������̖͗l�̓d�q�z�M�Ȃǂ��s���Ă���B
�@���̎���������I��JCI�z�[���y�[�W�̍X�V�Ɍ����V���ȑg�D�Â������悵�A
2015�N�ɐݒu���ꂽ�u���R�~���j�P�[�V�����ψ���v�Ƀz�[���y�[�W�Ɋւ�鏊�ǂ��ڍs���A
�d�q��ψ���͖{���̓d�q��Ɋւ��x���g�D�Ƃ��ĕs����Ȉψ���ւƉ��g�����B
|
|
|
|
| �d�q��ψ���̊��� |
|
|
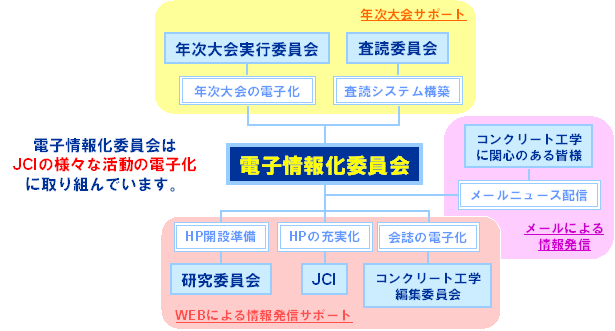 |
|
| �@�d�q��ψ����2002�N�x�ɔ������Ĉȗ��C��̂ł���d�q������̊��������p���Ȃ���C��}�Ɏ����悤��JCI�̗l�X�Ȋ����ɂ܂œd�q��̌����Ώۂ��L���C�ϋɓI�ɓd�q���Ɏ��g��ł��܂��B |
|
|
|
| �i�b�h�̊����̓d�q��� |
| ����@���@�i�d�q��ψ���ψ����j |
| �R���N���[�g�H�w�CVol.43�CNo.9�Cpp.73-75�C2005.9 |
|
| 1.�@�ړI�ƌo�� |
| �@�d�q��̈Ӌ`�ɂ��ẮA�����̏ȃX�y�[�X�ł̕ۑ��A�l�X�ȓd�q�����ւ̑Ή��A�C���^�[�l�b�g�𗘗p���Ă̏�M�A�������E�ȗ͉�������������B |
|
�@�@JCI�����̓d�q��̂��߂̑�1�X�e�b�v�Ƃ��āA�N�����̊w�p�u����̘_���̓d�q���e�V�X�e�����\�z�E�^�p���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA200�P�N�ɔN�����Q�O�O�Q�i���j���s�ψ���i�ψ���:�R�{�וF�E�}�g��w�����j�ɓd�q������i���:�ێR�v��E�����Z�p�Ȋw��w�����j���ݒu���ꂽ�B�ψ��̍\���ɂ��ẮA2002�N�x�ɔ��������d�q��ψ���i�ψ���:�ێR�v�ꋳ���A2003�N�x����́A���
���E��t��w�����j�̉��L��URL�̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă���B
http://www.jci-web.jp/denshi/ |
|
| 2.�@�d�q������̊����i2001�N�x�`2002�N�x�j |
�@���̓d�q������̊������e�́A
�E�d�q�\�����݁E�d�q���e���{�̋�̓I��ƂɌW��錟��
�E�d�q���ɔ����A������Ɋ֘A���鎖���̘A�g���
�E2002�N(����)�Ɍ��肹���A�d�q���ɌW��鏫���v��
�ł������B |
|
| �@�_�����e�V�X�e���̓d�q���ɂ��Ă͓y�؊w��Ŋ��ɍs���Ă���A�Q�l�ɂ��鏊�������������B�d�q���e�V�X�e���̃\�t�g�J���֘A�Ƃ��ẴT�[�o�[�̊Ǘ��A�^�c�A�₢���킹�����A���p�z�[���y�[�W�̊J�݁A�v���O�����Ґ��p�����̍쐬�A���e�_�������߂�CD-ROM�̍쐬�Ȃǂ́A�A�E�g�\�[�V���O�Ƃ��Ă̊O�����邱�ƂŁA�����ǂȂǂ̍�Ɨʂ̒ጸ����}��A�d�q������ł̓t���[�������߂��Ƃ����S�ƂȂ����B |
|
| �@�d�q������ł́A���ɘ_�������̔}�̂���CD-ROM�ɕύX����Ӌ`�m�ɂ���ƂƂ��ɁA���̃����b�g��l�X�ȕ��@�ŗL���Ɋ��p����K�v�����邱�Ƃ��R�c���ꂽ�B |
|
�@2002�N�̂��Α��ł́A�N���_���W�Ȃǂ̓d�q���Ɍ����āA���̂悤�ȗl�X�ȐV�������݂���������A�������ꂽ�B
�E �C���^�[�l�b�g�𗘗p�����d�q�\������
�E ���ʂł̍��nj��e�̓��e
�E �C���^�[�l�b�g�𗘗p�����ŏI���e�̓d�q���e
�E CD-ROM�Ƃ��ẴR���N���[�g�H�w�N���_���W��24���̔���
�E �_���̃^�C�g���A�L�[���[�h�A���ғ��ɂ�錟���V�X�e���̓���
�E ���Α��ւ̃C���^�[�l�b�g�𗘗p�����d�q�\�����݂ɂ��Q�� |
|
| �@CD-ROM�Ƃ��ẴR���N���[�g�H�w�N���_���W��24���̃f�U�C����}-�P�Ɏ����BCD-ROM�P�[�X�̗��\���ɂ́A�N�����̃|�X�^�[�E�f�U�C�����������A�}-�Q��a)�`d)�Ɏ����悤�ɁA2002�N���Α��́u�l�Z�i���낭�j�̂��܁v�A2003�N���s���́u�͂�Ȃ�R���N���[�g�v�A2004�N���m���́u�R���N���[�g�ېV�v�A2005�N���É����́u������n��R���N���[�g�U�v�ȂǂƁA�|�X�^�[�̃C���[�W����A�e���̌����v���o����`�ƂȂ��Ă��邱�Ƃɂ��Ӌ`������B |
|

�}�|�P�@�b�c�|�q�n�l�Ƃ��ẴR���N���[�g�H�w�N���_���W
��24���i2002�N���Α��j�̃f�U�C�� |
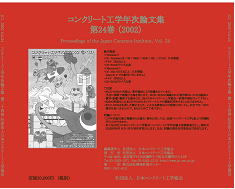
a) 2002�N���Α��́u�l�Z�i���낭�j�̂��܁v
�����ɂ́u�G�R���W�[���R���N���[�g�D2002�v |
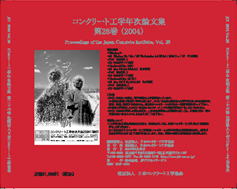
c) 2004�N���m���́u�R���N���[�g�ېV�v
|
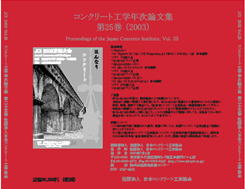
b) 2003�N���s���́u�͂�Ȃ�R���N���[�g�v
|
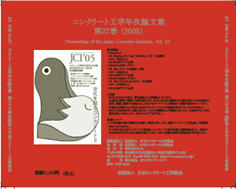
d) 2005�N��������
�u������n��R���N���[�g�U�v |
| �}�|2 CD-ROM�P�[�X�̗��\�� �i�N�����̃|�X�^�[�f�U�C�����������Ă���j |
|
�@�N�����̓d�q���ɑ���A���Α��ł̃A���P�[�g���ʂ́A�R���N���[�g�H�w��2002�N10�����ł��Љ�ꂽ���ACD-ROM�Ř_���W�̌p���ɁA��80���̎^��������ꂽ���A�����@�\�̉��P�̕K�v���w�E���ꂽ�BWeb��ł̎Q���o�^�⌴�e��o���֗��������Ƃ��������ꂼ��A73���A78���ɒB���APDF�`���̗̍p��86���̎^��������ꂽ�B
�ihttp://www.jci-web.jp/denshi/bukaiwork.html�@�ɂăA���P�[�g���ʂ����J���Ă��܂��B�j |
|
| �@���̌�̌����ۑ�Ƃ��āA�y�[�p�[���X�̘_�����ǃV�X�e���Ƙ_���t�@�C���̃_�E�����[�h�Ɖۋ��V�X�e���̍\�z��������ꂽ�B |
|
| �@���Ljψ���ɂ����_���̍��ǃV�X�e���ɂ��Ă��A�C���^�[�l�b�g�̗��p�ɂ��A���Ljψ��̃f�[�^�x�[�X�ɂ��������A���ǂ̓d�q�����ɂ��A�������A�ȗ͉����}��ꂽ�B |
|
| 3.�@�d�q����ψ���̊����i2002�N�x����j |
| 3.1�@2002�N�x�̊��� |
�@2002�N9�����甭�������d�q��ψ���ł́A
�E �N�����̓d�q���̃T�|�[�g
�E ���s���ʼnғ����鍸�ǃV�X�e���̊���
�E JCI�̗l�X�Ȋ����̓d�q���i�ߋ��̕����̓d�q���A�ۋ��V�X�e���Ȃǁj
�E ACI�Ƃ̃����N�i�o�ŕ��̑��ݍw���Ȃǁj
�Ȃǂ�����g�݁A�N�����̘_���W��CDROM���A�_���̓��e�A���ǃV�X�e����Web���Ȃǂ�B�����A�����̖ړI�͂قڒB�������i�K�ɂ���B |
|
| 3.2�@2003�N�x�̊��� |
| 3.2.1�@���[���j���[�X |
| �@2003�N�x����́AJCI�����̓d�q��̌����Ώۂ��L���AJCI�̃z�[���y�[�W�̏[�����A�R���N���[�g�H�w���̓d�q���A�����ψ���̈ψ�����ł̃z�[���y�[�W�̊��p�ƌ������ʂ̓d�q���Ɍ����Ẳۑ蓙�̌����Ɏ��g��ł����B |
|
| �@�R���N���[�g�H�w�̓���I�ȕω�������ɓ`���邽�߂ɂ́A���}�̂̉�ɉ����āA�z�[���y�[�W���g�I�ȗ���Ȃ̂��ӂ݂āA�z�[���y�[�W�̍X�V���v���ɏ�M����HP�ւ̉{���̋@��𑝂₵�Ă������߂ɂ��A����ɐV�������̑��݂�`�����i�Ƃ��āA���[���j���[�X��9����������{����\��ł���B |
|
�@���[���j���[�X�̈Ӌ`�E�����E���ӓ_�Ƃ��ẮA���̂��Ƃ��l������B
�E HP�Ȃǂ����ɍs�����߂̐V���Љ�c�[��
�E �R���N���[�g�H�w�������s��ɁA�ڎ������炽�߂ďЉ�ĉ{���̍Ċm�F�𑣂������b�g����B
�E JCI��̓d�q�Łi���ʂœ��e���킩��悤�ɁAHP�ւ̃n�C�p�[�����N�g�p�j
�E �o�������R���p�N�g�Ȃ��̂Ɂi�T�v���g�b�v���ʂɁA�ڍׂ́A���̌�ɍ��ڂ���ׁA�ڍׂ̓n�C�p�[�����N�ŕʂ�Web�T�C�g�ʼn{������`�Ƃ���ȂǁB�j
�E JCI�̏�������I�ɓ`������
�E �g�߂ɂȂ��Ă������[���ɂ��JCI�̊���������ɓ`����B�i���̂��Ƃ́AJCI�̗l�X�Ȋ��������@�d�q�����Ă�����삯�ɂ��Ȃ�B�Ⴆ�A�R���N���[�g�H�w���A�ψ�����AHP�̏[�����Ȃǁj
�E ����ʂ̃A�h���X�Ǘ����L�p�B�i�V���|�W�E������PR��ψ�����̌Ăт����ȂǂɁj
�E 1�����ɂP����x�A�p���I�Ƀ��[���j���[�X���^�p�ł���悤�ɁA�����̂Ȃ��^�c�E�Ǘ���S������B
�E ���̂悤�Ƀ��[���j���[�X�́A����ւ̓���I�ȏ�M�Ƃ��ėL�p�Ȃ��Ƃ���A���̌p���I�ȃ\�[�X�̊m�ۂƏ��̓��e��ی�ɐT�d�ȉ^�c�E�Ǘ��ɗ��ӂ��āA�ϋɓI�Ɏ��{�������B |
|
| �@���[���j���[�X�̔��s�͖����A�����́A�R���N���[�g�H�w�����s����2�T�Ԍ���x�Ƃ��A���[���j���[�X�́AJCI�̎����ǂƓd�q��ψ����S�����ĉ^�c���Ă����B |
|
| 3.2.2�@�����ψ���̃z�[���y�[�W |
�@�����ψ���Ɋւ��ẮA
�E ����ł́A�ψ���g�D��ψ���c���^�A���������v�����Ɍf�ڂ���Ă��Ȃ����ψ�������B
�E �����ł̊J�Â������̂ŁA�n���̉���͏o�Ȃ�����V���|�W�E���Ȃǂ̊J�Ó��e�⌤�����ʂ̈ꕔ���v������ŏЉ�ł���ƗL�Ӌ`�ł���B�i���́A�T�|�U�s�Ŋ����ړI�Ɗ������e���L�ځj
�E ���ʂ̓d�q�t�@�C����ۑ������łȂ��A���p�@���l����ׂ��B�i������L���c�k���j�@
�E �p���̏�������Ƃ悢�B
�Ȃǂ̋c�_������A�d�q��ψ���Ƃ��ẮA�����ψ�����ψ���̊������e��Web�ł̏Љ�̑��i��}��ړI�ŁA�ψ�����Љ�ɓ��������W���`���i�ЂȌ`�A�e���v���[�g�j�̃z�[���y�[�W�iHP�j�̍쐬�����݂��B |
|
| �@�����ψ���ɂ́A���ψ�������e�̕W���z�[���y�[�W�ւ̌f�ڂ����肢���Ă���B�������ψ���̃z�[���y�[�W�̍X�V�Ȃǂ��A9������J�n���郁�[���j���[�X�ŏЉ�ł���A�z�[���y�[�W�ւ̉{���҂����₹��̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂��Ă���B |
|
�@���Ȃ݂ɁA�d�q��ψ�������L��URL�̃z�[���y�[�W�Ŋ����̏Љ���s���Ă���B
http://www.jci-web.jp/denshi/ |
|
| 3.2.3�@JCI�z�[���y�[�W�̉��P��\�[�X�̃f�B�W�^���� |
�@JCI��Web�T�C�g�Ƃ��Ẵz�[���y�[�W�́A�����ǂ𒆐S�ɉ^�c�Ǘ�����Ă��邪�AJCI�̍L�͈͂̎Љ�I�����𑍍��I�Ƀo�����X�悭�Љ��ϓ_����́A�K��������т����l�����ɉ������v���Ȃ���Ă��Ȃ���������B����A�e���ڂ̕K�v���̋ᖡ������s���ƂƂ��ɁA�R���N���[�g�H�w�̋����[�����̒~�ςƍL�K�v�ł���B
�E ���ꊴ�ƃo�����X
�E �R���N���[�g�H�w�̐��ʂ̃O���t�B�b�N�X�Љ�̃y�[�W�ȂǁF�ŋ߂̃R���N���[�g�\�����A���j�I�\�����Ȃ�
�E ���C���e�i���X�ƒS���g�D�̂�����i��C�����{�A�E�g�\�[�V���O�A�z�[���y�[�W�ψ���������͓d�q��ψ���j
�E �A���V�X�e���i�\�[�X�̎��W���@�j |
|
�@�R���N���[�g�H�w���̃f�B�W�^�����Ƃ��̊��p�ɂ��ẮA
�E �\���Ȃǂ̎ʐ^��ꕔ�̓��e���v�����Ɍf�ڂ��Ă��ǂ��̂ł́B�D�ꂽ�ʐ^��O���t�B�b�N�X���R���N���[�g�H�w���ɂP�����̏Љ�ɏI���̂͂��������Ȃ��Ƃ̎w�E������B
�E �o�b�N�i���o�[�̋L���̌������ł���ƗL�p�ł���B�i�o�b�N�i���o�[�̃f�B�W�^�����j
�E �P�N���̂b�c�q�n�l�����L�p�B
�Ȃǂ̒�Ă�����B |
|
| 4.�@�ނ��� |
| �@2001�N�x����̓d�q�����d�q��ψ���̊�������A�N�����̓d�q���A�_�����ǃV�X�e���̓d�q���A���[���j���[�X�A�����ψ���̃z�[���y�[�W���ւ̊������ʂ��Љ���B |
|
| �@JCI�ł́A40���N�L�O���Ƃ̒��ŁAJCI�̊�{���̓d�q�����s��ꂽ�B����A���̊�{���̓d�q�f�[�^�̊��p�@���������Ă������Ƃ��ۑ�ł���B�܂��A�ߋ��̌������̓d�q���ɂ��A�N���_���W�̑�1������S�Ă̘_�����z�[���y�[�W��Ō����ł���悤�ɂȂ������ACD-ROM�łƂ��Ă̍ŋ߂̘_���̗L���_�E�����[�h�ȂǁA�_���������p�̏[�������ۑ�ł���B |
|
| �@����AJCI�̃z�[���y�[�W�̂�����AJCI�̗l�X�ȃ��\�[�X�̓d�q���ȂǁAJCI�̎��������ȊO�̗l�X�Ȋ����ɂ��āA�o����͈͂���d�q����āA�����̊���������I�ɉ���Ɍ�����`�ɂ��Ă��������ƍl���Ă���B |
|

